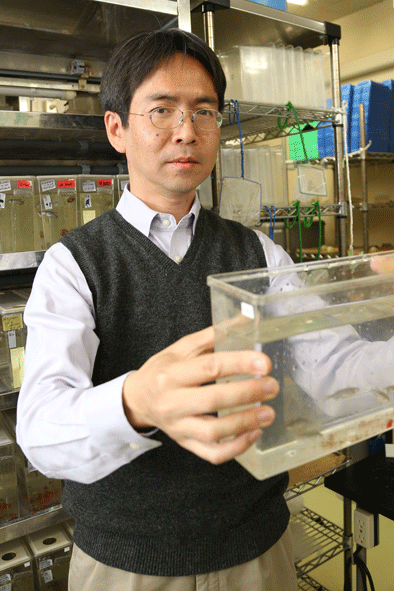

・2024/11/12 令和6年度主任研究員研修@農研機構(Zoom)で小林がワークショップを開催しました。
・2024/11/9 赤血球研究シンポジウム@東京で小林が講演しました。
・2023/11/17 令和5年度主任研究員研修@農研機構(Zoom)で小林がワークショップを開催しました。
神戸生まれの湘南育ち。小学生からサッカー三昧。
慶應義塾大学理工学部化学科3期。土橋源一・太田博道研では微生物を利用した有機合成。修士は医学部に出向し、清水信義研で細胞生物学を学び、がん細胞のシグナル伝達機構を研究。博士は総研大1期生として、石浜明研で大腸菌とインフルエンザウイルスの転写機構を題材に、生化学と研究姿勢を鍛えていただいた。
国立遺伝研(石浜研)での学振特別研究員PDを経て、自治医大助手に着任。長野敬・川上潔研では、Naポンプの遺伝子発現制御の研究に従事。米国NIHのDawid Igor研に1年間出向し、ゼブラフィッシュを用いた発生生物学研究とともに遺伝子単離を初めて行う。帰国後もゼブラフィッシュを活用。
1998年より筑波大の山本雅之研。ゼブラフィッシュを活用した造血発生とストレス防御の研究を開始。科技機構ERATO山本環境応答プロジェクト 順方向遺伝学グループリーダ併任して、突然変異系統の大規模スクリーンを行う。山本先生の東北大異動後は研究室を主催。発生のしくみとストレス応答のしくみの研究している。切り口はエピジェネティクス制御を含む遺伝子発現制御で、動物解析にはゼブラフィッシュを活用している。
近年は、1)食品成分の機能性、2)各種ストレス応答・防御のメカニズム、3)個体発生・細胞分化における遺伝子発現制御、4)記憶学習のエピジェネティクス制御、5)ヒト疾患モデルや毒性試験モデルの構築、を研究している。
なお、2006年より芸術学系の田中佐代子先生とサイエンスビジュアル教育を開始。2010年には、田中・三輪佳宏先生とともに日本サイエンスビジュアリゼーション研究会を設立。以後、関連する講演活動も行っている。
医学の基礎(分子細胞生物学)[医学類]
細胞・発生工学[医療科学類]
医科分子生物学[医療科学類]
基礎医学総論[医療科学類]
イメージング総論[医療科学学類・芸術専門学類]
人間生物学コース(分子発生生物学概論)[生物学類]
医科学セミナーV(キャリアパス)[フロンティア医科学]
医学研究概論(研究不正の防止)[生命システム医学]
Serendipity in Human Science[ヒューマンバイオロジー]
研究のビジュアルデザイン[人間総合学術院共通科目]
巨人の肩に立つ−生命医科学の歴史と未来−[人間総合学術院共通科目]
発生生物学[法政大学 生命科学部]
遺伝子発現制御は生命科学の根本です。学生時代から研究してきましたが、謎は謎のまま。わかってきたことも山ほどありますが、登場分子がどんどん増え、複雑化の一途をたどってます。かわいい熱帯魚ゼブラフィッシュを使って、謎の一端を解きたいと思っています。
サイエンスには仮説を立てて実験し、予想通りでも予想外でも結果を考察する楽しさがあります。特に生命科学には意外な現象が満載で、天才でなくても大発見できるチャンスがあります。うまくいかないことは多く、泣きたくなることも少なくないです。だからこそ困難を突破したときの喜びは何ものにも代え難いです。医科学には、自分の発見が医療や創薬につながる可能性もあります。
私たちの研究に興味をもったなら、ぜひ一緒にサイエンスをやりませんか。将来研究者にならなくても、サイエンスの経験は大きな財産になると思います。
一村雨の雨宿り(縁は大切)
@は全角になっています。半角に打ち直してメールしてください。