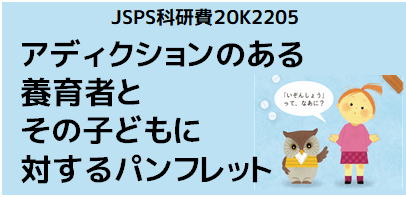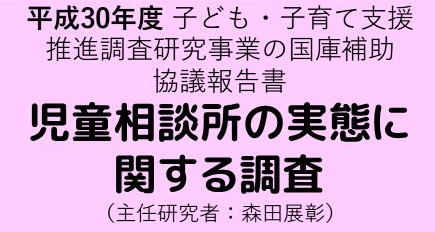メンバーmembers
トップページ メンバー
メンバー 大谷助教のプロフィール
大谷助教のプロフィール
(「ヒューマン・ケア科学専攻への招待」より抜粋)
「神よ、変えられるものについてはそれに立ち向かう勇気を、変えることのできないものについてはそれを受け入れる落ち着きを、そして両者を見極めるための賢さを、私に与えたまえ」。これは、神学者であり政治学者でもあったラインホルド・ニーバーの“平安の祈り(Serenity prayer)”と呼ばれる言葉です。様々な困難に直面した際に持つべき心の姿勢について、その要点が簡潔に整理され述べられており、個人的にとても思い入れがあります。
この「祈り」と私は、形を変えて2回出会うことになります。1回目は私がまだ大学院生の頃です。当時、私は心理学専攻の社会心理学研究室に所属しており、心の問題のメカニズム解明に社会心理学の立場から貢献できないかと考え、抑うつ・不安・強迫・摂食障害などさまざまな心の問題と関連するリスク要因である完全主義(Perfectionism)について研究していました。完全主義とは自分の行動評価に完全性を求める人格傾向のことを指します。
完全主義者は自分の失敗や欠点を許容することが極度に苦手です。だから失敗を犯さないよう強迫的な努力を重ねますが、どんなに努力しても自分の遂行に満足できないため、自己評価は低下し精神的健康は悪化します。彼らにとって重要なのは「自身にとって期待外れやコントロールできない部分の存在を認め,それを無害/ポジティブなものとして捉え直し共存すること」です。ニーバーの祈りに照らし合わせると、「できないものについてそれを受け入れる落ち着き」が必要だということです。博論執筆時にこの言葉を知った私は、テーマの本質を突いていると気に入って後書きに載せたりしたものです。
2回目は私が前職の研究所で薬物・アルコールなどの物質依存(Substance disorder)について研究していた頃です。物質依存とは、社会生活上差し障りが生じても、なお依存性物質の連続的な使用を自ら止めることができない病気です。治療するには物質使用を完全に止めるしかありませんが、いったん依存状態に陥ると、せっかく断薬をしてもふとしたきっかけで物質渇望感が再燃するため、再発率の非常に高い病気でもあります。
また依存が進むと、脳が変化して薬物・アルコールの接種を第一とする考え方に変貌していきます。代表的なのは、歪んだ物質統制感(自分は薬物をきちんとコントロールできている。危険はない)と、問題認識の低さ(自分は依存症ではないし、問題はない)です。治療を進めるには、まずこういった認識を改め、「自分は問題に陥っており、自身の力ではどうにもならない」と認めることが大事になってきます。
ところが依存症においては、物質使用により付随的に現われる幻覚などの症状を抑える薬はありますが、中心的問題である渇望感を抑える薬は今のところありません。したがって依存そのものの治療は心理社会的なものが中心になります。それまで薬物やアルコール中心の生活をしてきた人が、依存物質を断ち切り続けるのは相当困難な作業です。個人の意志の力だけで簡単にどうにかなる問題ではありません。
それではどうするか。依存症自体の治療は自助グループ(「ダルク」や「アルコホーリクス・アノニマス」などが有名です)と呼ばれるグループ治療が盛んに行われています。患者さん同士が集まって悩みや不安を吐露しながら共に薬やアルコールをやめ続けようと試行錯誤します。アメリカ発祥の「12ステップ・プログラム」と呼ばれる回復プログラムが使われるのですが、プログラム実施前に全員で唱和されるのが、冒頭のニーバーの祈りなのです。
完全主義と依存症の両者は対極にあるようにも見えますが、そこに通底するのは、問題を打破するには「今まで自分を支えてきた柱を断念する」必要があるということです。強迫的な努力を続けて完全な自分という幻想を維持すること、依存物質を使用することで自らの欠損を埋め、簡単にかりそめの幸福感を手に入れることを、彼らはそれぞれ生きる支えにしてきたからこそ、簡単にはそれを手放せないのでしょう。
上手に断念するのは時間のかかる難しい作業です。重要なのは、「ひとつでも失敗したら人生終わりに決まっている」「薬物を使わない人生など考えられない」など「自身の中でわかったつもりになって完結してしまう状態」に陥らないことです。個人内で思考の泥沼に陥らないために、時には共感し、時には異なる見解を投げかける他者が混ざった状況をあえて用意するのがグループ治療のエッセンスです。どのような方向であれ、自身の問題に対峙しつつ進んでゆくには、自身だけでなく他者をはじめとする自分以外のものの力が必要になる。それこそがヒューマン・ケアの本質の一つなのだと考えます。
最後に私の個人的な思い出を加えれば、博論の後書きに載せたこの言葉に対して、明田芳久先生――当時大変な闘病生活を送りながらも最後まで懇切丁寧に論文を見てくださった今は亡き私の指導教員――から「…これは今の私の祈りでもあります」と伝えていただいたのが忘れられません。師匠と思いを共有した経験を通して、この言葉は私にとって今でも大きな力を持って語りかけてくるのです。
助教 Assistant Professor
大谷 保和 Yasukazu Ogai
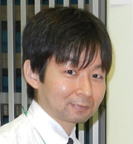
| 専門領域 | 臨床社会心理学 |
| 研究テーマ | 完全主義が精神的健康に及ぼす影響とそのメカニズム アルコール・薬物依存症の重症度・再発リスクの測定と臨床応用 依存症に対するさまざまな治療法(認知行動療法・診療薬・回復プログラム)の効果 |
| 詳細な プロフィール |
TRIOSのプロフィールページ 業績一覧(本ホームページ内) |
ショートエッセイ
ニーバーの祈り:完全主義と依存症をつなぐもの(「ヒューマン・ケア科学専攻への招待」より抜粋)
「神よ、変えられるものについてはそれに立ち向かう勇気を、変えることのできないものについてはそれを受け入れる落ち着きを、そして両者を見極めるための賢さを、私に与えたまえ」。これは、神学者であり政治学者でもあったラインホルド・ニーバーの“平安の祈り(Serenity prayer)”と呼ばれる言葉です。様々な困難に直面した際に持つべき心の姿勢について、その要点が簡潔に整理され述べられており、個人的にとても思い入れがあります。
この「祈り」と私は、形を変えて2回出会うことになります。1回目は私がまだ大学院生の頃です。当時、私は心理学専攻の社会心理学研究室に所属しており、心の問題のメカニズム解明に社会心理学の立場から貢献できないかと考え、抑うつ・不安・強迫・摂食障害などさまざまな心の問題と関連するリスク要因である完全主義(Perfectionism)について研究していました。完全主義とは自分の行動評価に完全性を求める人格傾向のことを指します。
完全主義者は自分の失敗や欠点を許容することが極度に苦手です。だから失敗を犯さないよう強迫的な努力を重ねますが、どんなに努力しても自分の遂行に満足できないため、自己評価は低下し精神的健康は悪化します。彼らにとって重要なのは「自身にとって期待外れやコントロールできない部分の存在を認め,それを無害/ポジティブなものとして捉え直し共存すること」です。ニーバーの祈りに照らし合わせると、「できないものについてそれを受け入れる落ち着き」が必要だということです。博論執筆時にこの言葉を知った私は、テーマの本質を突いていると気に入って後書きに載せたりしたものです。
2回目は私が前職の研究所で薬物・アルコールなどの物質依存(Substance disorder)について研究していた頃です。物質依存とは、社会生活上差し障りが生じても、なお依存性物質の連続的な使用を自ら止めることができない病気です。治療するには物質使用を完全に止めるしかありませんが、いったん依存状態に陥ると、せっかく断薬をしてもふとしたきっかけで物質渇望感が再燃するため、再発率の非常に高い病気でもあります。
また依存が進むと、脳が変化して薬物・アルコールの接種を第一とする考え方に変貌していきます。代表的なのは、歪んだ物質統制感(自分は薬物をきちんとコントロールできている。危険はない)と、問題認識の低さ(自分は依存症ではないし、問題はない)です。治療を進めるには、まずこういった認識を改め、「自分は問題に陥っており、自身の力ではどうにもならない」と認めることが大事になってきます。
ところが依存症においては、物質使用により付随的に現われる幻覚などの症状を抑える薬はありますが、中心的問題である渇望感を抑える薬は今のところありません。したがって依存そのものの治療は心理社会的なものが中心になります。それまで薬物やアルコール中心の生活をしてきた人が、依存物質を断ち切り続けるのは相当困難な作業です。個人の意志の力だけで簡単にどうにかなる問題ではありません。
それではどうするか。依存症自体の治療は自助グループ(「ダルク」や「アルコホーリクス・アノニマス」などが有名です)と呼ばれるグループ治療が盛んに行われています。患者さん同士が集まって悩みや不安を吐露しながら共に薬やアルコールをやめ続けようと試行錯誤します。アメリカ発祥の「12ステップ・プログラム」と呼ばれる回復プログラムが使われるのですが、プログラム実施前に全員で唱和されるのが、冒頭のニーバーの祈りなのです。
完全主義と依存症の両者は対極にあるようにも見えますが、そこに通底するのは、問題を打破するには「今まで自分を支えてきた柱を断念する」必要があるということです。強迫的な努力を続けて完全な自分という幻想を維持すること、依存物質を使用することで自らの欠損を埋め、簡単にかりそめの幸福感を手に入れることを、彼らはそれぞれ生きる支えにしてきたからこそ、簡単にはそれを手放せないのでしょう。
上手に断念するのは時間のかかる難しい作業です。重要なのは、「ひとつでも失敗したら人生終わりに決まっている」「薬物を使わない人生など考えられない」など「自身の中でわかったつもりになって完結してしまう状態」に陥らないことです。個人内で思考の泥沼に陥らないために、時には共感し、時には異なる見解を投げかける他者が混ざった状況をあえて用意するのがグループ治療のエッセンスです。どのような方向であれ、自身の問題に対峙しつつ進んでゆくには、自身だけでなく他者をはじめとする自分以外のものの力が必要になる。それこそがヒューマン・ケアの本質の一つなのだと考えます。
最後に私の個人的な思い出を加えれば、博論の後書きに載せたこの言葉に対して、明田芳久先生――当時大変な闘病生活を送りながらも最後まで懇切丁寧に論文を見てくださった今は亡き私の指導教員――から「…これは今の私の祈りでもあります」と伝えていただいたのが忘れられません。師匠と思いを共有した経験を通して、この言葉は私にとって今でも大きな力を持って語りかけてくるのです。
お問い合わせビルダークリニック
〒305-8577
茨城県つくば市天王台1-1-1
総合研究棟D743室
E-mail:
![]()