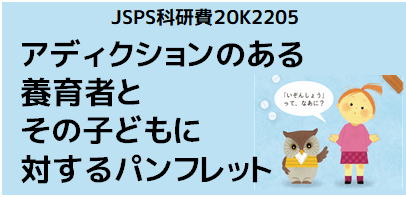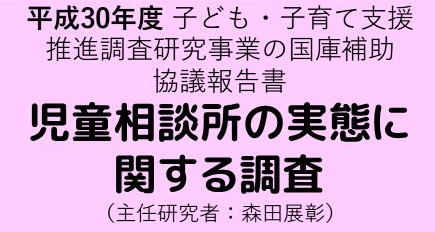メンバーmembers
トップページ メンバー
メンバー 斎藤客員教授のプロフィール
斎藤客員教授のプロフィール
ショートエッセイ
ひきこもり研究から見える“多元主義”の未来
私は1986年に筑波大学医学専門学群を卒業し、1990年に筑波大学大学院環境生態系で医学博士を取得後、千葉県船橋市にある爽風会佐々木病院に四半世紀ほど勤務しました。昨年、約20年ぶりに母校に戻って来る直前まで、常勤医として、外来と入院病棟を担当していたのです。
私の出発点は、大学院在籍時代の臨床現場における「社会的ひきこもり」との出会いでした。
当時はまだ呼び名も概念も定まっておらず(現在もですが)、海外での事例報告や先行研究もない状態で、大学病院の外来に殺到する患者さんやその家族の対応に途方に暮れていたことを覚えています。故・稲村博先生の指導のもと、手探りで治療研究を続け、その成果の一部が学位論文となりました。
さらに、この論文に基づいて書き下ろした新書『社会的ひきこもり』(PHP研究所)は私の唯一のベストセラーとして、国内外で大きな反響を呼びました。2013年3月にはミネソタ大学出版局から英訳(Hikikomori: Adolescence Without End)も出版されています。
いまやわが国には、ひきこもり事例が約70万人存在すると推定され(内閣府調査、2010年)、精神医学においてのみならず、特異な社会問題としても国際的にも広く知られています。オックスフォード英語辞典にも収録された“hikikomori”という言葉は、もともと筑波大学社会医学系においてその研究に先鞭がつけられ、大きく発展していった概念なのです。
この発祥と揺籃の地に教官として戻って来たことには、偶然を越えた運命めいたものの導きを感じずにはいられません。
さて、ひきこもりに限ったことではありませんが、いわゆる「現代型うつ」の増加などに象徴されるように、現代の精神疾患は軽症化しつつその領域を拡大しつつあります。
とりわけ「サブクリニカル」な問題領域は、青少年のメンタルヘルスを中心に臨床的な比重を増しつつあります。例えば不登校、虐待、いじめ、ひきこもり、自傷、家庭内暴力、発達障害、薬物乱用などの問題は、日常臨床でしばしば接する問題でありながら、精神医学においては依然として周縁的な領域とみなされがちです。このため、急増する現場の需要に対して、専門家の育成がほとんど追いついていません。
いまや精神医学の主流は生物学的精神医学ですが、こうしたサブクリニカルな問題群を取り扱うには、生物学的視点のみでは限界もあります。時には精神病理学(精神分析)的視点や家族療法的視点、さらに疫学的視点が欠かせません。これは、軽症事例ほど家庭や学校といった環境要因の影響を大きく受け、環境との相互作用で疾病システムを構成するため、治療に際しては時に周辺環境に対しても適切に介入する必要があるためです。
こうした問題に対しては、従来Bio-psycho-socialという折衷主義的モデルが適切であるとされてきました。しかし、アメリカの精神科医Ghaemi,N.は、折衷主義よりも多元主義(pluralism)の立場を強く提唱し、近年注目されています。
この立場は簡単に言えば、理論を「いいとこ取り」的につまみ食いする折衷主義を批判しつつ、治療と研究の局面ごとに、有効性において最も優位な理論を一つ採用する、というものです。
これは比喩的に言えば、画像データは画像ソフトで、文書データはワープロソフトで開くような発想です。原理主義的な硬直性や、折衷主義的な恣意性に陥らずにすむという点では、大きなメリットがあると考えられます。
例えばGhaemi,N.は、客観的事象間の因果関係の説明としては自然科学的な「説明」Erklaerenを採用し、患者の主観や個別的な現象を理解する際には「了解」Verstehen(ヤスパース)のほうを採用する、としています。
私自身の専門に関連づけるなら、ひきこもり事例に治療的に関わる際には、まさに多元主義的であるほかはありません。家族相談においてはシステム論、個人精神療法は精神力動論、発達障害との関連については生物学、マクロの分析には疫学的視点がそれぞれ有効となるからです。
ちょっと手前味噌になりますが、私は臨床家としてひきこもり事例の治療に関わるかたわらで、思想的あるいは倫理的側面から「精神科臨床はいかにあるべきか」をずっと考え続けてきました。実は私の最初の著作『文脈病−ラカン・ベイトソン・マトゥラーナー』(青土社)は、人間の主体のありようを「分析的主体」と「器質的主体」に区分し、両者をシステム論的に架橋するという意味で、きわめて多元主義的な試みであったと自負しています。
目下の私の最大のテーマは、四半世紀にわたりかかわってきたひきこもり研究を総括しつつ、あらためて多元主義的な視点からこの問題を整理し、現状の把握と有効な支援の確立を進めることです。
ひきこもりの疫学調査においては、従来のアンケート回収方式の限界を踏まえつつ、より正確な推計を可能にするような手法の検討を、また臨床面においては治療的支援を継続しつつ、とりわけ学内のひきこもり学生を対象として、アウトリーチなどの手法も取り込んだ予防的支援を実施したいと考えています。
すでに国外においてもひきこもりへの関心は急速に高まりつつあり、韓国やイタリアの精神科医とは現在も交流があります。わが国のひきこもり支援現場における多様な経験の蓄積は、今後国際的な支援の現場でも指導的な立場を担うことになると考えられます。
ひきこもり問題の周縁性は、見方を変えれば最大の可能性でもあります。その本質的理解には、医学のみならず、心理学、社会学、福祉などの諸領域の学際的な視点が要請されます。こうした視点は学群教育や臨床教育においても、社会的環境との関わりの中で臨床をとらえるような広い視野を醸成してくれるでしょう。本学の柔軟で多様性に開かれた教育環境のもと、多くの優れた臨床家や高度専門職業人の養成に関わることができれば、これにまさる幸いはありません。
幸い本研究室には、もう一つの周縁領域とも言える児童虐待や依存症を専門とする森田展彰准教授をはじめ、内外に数多くの優れた専門家のネットワークがあります。私もその一員として、本学のいっそうの発展と地域医療の充実、さらには精神医学全体の進歩に寄与したいと考えております。
このページの
客員教授 Visiting Professor
斎藤 環 Tamaki Saito

| 専門領域 | 思春期・青年期の精神病理学・病跡学 |
| 研究テーマ | 不登校・社会的ひきこもりなどに関する精神医学的な評価と支援のあり方、発達障害との関連性、疫学的アプローチ、国際比較研究、学際的な概念の整理 |
| 詳細な プロフィール |
ショートエッセイ
ひきこもり研究から見える“多元主義”の未来私は1986年に筑波大学医学専門学群を卒業し、1990年に筑波大学大学院環境生態系で医学博士を取得後、千葉県船橋市にある爽風会佐々木病院に四半世紀ほど勤務しました。昨年、約20年ぶりに母校に戻って来る直前まで、常勤医として、外来と入院病棟を担当していたのです。
私の出発点は、大学院在籍時代の臨床現場における「社会的ひきこもり」との出会いでした。
当時はまだ呼び名も概念も定まっておらず(現在もですが)、海外での事例報告や先行研究もない状態で、大学病院の外来に殺到する患者さんやその家族の対応に途方に暮れていたことを覚えています。故・稲村博先生の指導のもと、手探りで治療研究を続け、その成果の一部が学位論文となりました。
さらに、この論文に基づいて書き下ろした新書『社会的ひきこもり』(PHP研究所)は私の唯一のベストセラーとして、国内外で大きな反響を呼びました。2013年3月にはミネソタ大学出版局から英訳(Hikikomori: Adolescence Without End)も出版されています。
いまやわが国には、ひきこもり事例が約70万人存在すると推定され(内閣府調査、2010年)、精神医学においてのみならず、特異な社会問題としても国際的にも広く知られています。オックスフォード英語辞典にも収録された“hikikomori”という言葉は、もともと筑波大学社会医学系においてその研究に先鞭がつけられ、大きく発展していった概念なのです。
この発祥と揺籃の地に教官として戻って来たことには、偶然を越えた運命めいたものの導きを感じずにはいられません。
さて、ひきこもりに限ったことではありませんが、いわゆる「現代型うつ」の増加などに象徴されるように、現代の精神疾患は軽症化しつつその領域を拡大しつつあります。
とりわけ「サブクリニカル」な問題領域は、青少年のメンタルヘルスを中心に臨床的な比重を増しつつあります。例えば不登校、虐待、いじめ、ひきこもり、自傷、家庭内暴力、発達障害、薬物乱用などの問題は、日常臨床でしばしば接する問題でありながら、精神医学においては依然として周縁的な領域とみなされがちです。このため、急増する現場の需要に対して、専門家の育成がほとんど追いついていません。
いまや精神医学の主流は生物学的精神医学ですが、こうしたサブクリニカルな問題群を取り扱うには、生物学的視点のみでは限界もあります。時には精神病理学(精神分析)的視点や家族療法的視点、さらに疫学的視点が欠かせません。これは、軽症事例ほど家庭や学校といった環境要因の影響を大きく受け、環境との相互作用で疾病システムを構成するため、治療に際しては時に周辺環境に対しても適切に介入する必要があるためです。
こうした問題に対しては、従来Bio-psycho-socialという折衷主義的モデルが適切であるとされてきました。しかし、アメリカの精神科医Ghaemi,N.は、折衷主義よりも多元主義(pluralism)の立場を強く提唱し、近年注目されています。
この立場は簡単に言えば、理論を「いいとこ取り」的につまみ食いする折衷主義を批判しつつ、治療と研究の局面ごとに、有効性において最も優位な理論を一つ採用する、というものです。
これは比喩的に言えば、画像データは画像ソフトで、文書データはワープロソフトで開くような発想です。原理主義的な硬直性や、折衷主義的な恣意性に陥らずにすむという点では、大きなメリットがあると考えられます。
例えばGhaemi,N.は、客観的事象間の因果関係の説明としては自然科学的な「説明」Erklaerenを採用し、患者の主観や個別的な現象を理解する際には「了解」Verstehen(ヤスパース)のほうを採用する、としています。
私自身の専門に関連づけるなら、ひきこもり事例に治療的に関わる際には、まさに多元主義的であるほかはありません。家族相談においてはシステム論、個人精神療法は精神力動論、発達障害との関連については生物学、マクロの分析には疫学的視点がそれぞれ有効となるからです。
ちょっと手前味噌になりますが、私は臨床家としてひきこもり事例の治療に関わるかたわらで、思想的あるいは倫理的側面から「精神科臨床はいかにあるべきか」をずっと考え続けてきました。実は私の最初の著作『文脈病−ラカン・ベイトソン・マトゥラーナー』(青土社)は、人間の主体のありようを「分析的主体」と「器質的主体」に区分し、両者をシステム論的に架橋するという意味で、きわめて多元主義的な試みであったと自負しています。
目下の私の最大のテーマは、四半世紀にわたりかかわってきたひきこもり研究を総括しつつ、あらためて多元主義的な視点からこの問題を整理し、現状の把握と有効な支援の確立を進めることです。
ひきこもりの疫学調査においては、従来のアンケート回収方式の限界を踏まえつつ、より正確な推計を可能にするような手法の検討を、また臨床面においては治療的支援を継続しつつ、とりわけ学内のひきこもり学生を対象として、アウトリーチなどの手法も取り込んだ予防的支援を実施したいと考えています。
すでに国外においてもひきこもりへの関心は急速に高まりつつあり、韓国やイタリアの精神科医とは現在も交流があります。わが国のひきこもり支援現場における多様な経験の蓄積は、今後国際的な支援の現場でも指導的な立場を担うことになると考えられます。
ひきこもり問題の周縁性は、見方を変えれば最大の可能性でもあります。その本質的理解には、医学のみならず、心理学、社会学、福祉などの諸領域の学際的な視点が要請されます。こうした視点は学群教育や臨床教育においても、社会的環境との関わりの中で臨床をとらえるような広い視野を醸成してくれるでしょう。本学の柔軟で多様性に開かれた教育環境のもと、多くの優れた臨床家や高度専門職業人の養成に関わることができれば、これにまさる幸いはありません。
幸い本研究室には、もう一つの周縁領域とも言える児童虐待や依存症を専門とする森田展彰准教授をはじめ、内外に数多くの優れた専門家のネットワークがあります。私もその一員として、本学のいっそうの発展と地域医療の充実、さらには精神医学全体の進歩に寄与したいと考えております。
このページの
お問い合わせビルダークリニック
〒305-8577
茨城県つくば市天王台1-1-1
総合研究棟D743室
E-mail:
![]()