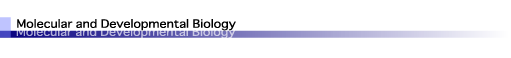
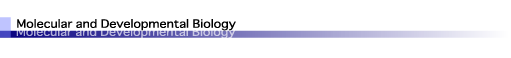
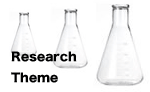 |
造血系で働く,転写因子GATA-2
|
|
|
遺伝子の発現調節とは,転写因子とは 遺伝子は,mRNAを作るコーディング領域と,その遺伝子の発現調節に働くノンコーディング領域からなっていますが,ノンコーディング領域の「GATA」配列を認識して結合し,その周囲にあるコーディング領域からmRNAを作らせる(あるいは作るのを止めさせる)指令を出すのが,転写因子であるGATA因子です.このように,さまざまな転写因子が,それぞれDNAの特別な配列を認識,結合し,周囲のmRNAの発現を活性化したり,抑制したりしています. |
||
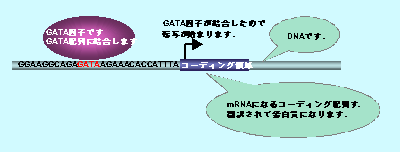 |
||
| 転写因子GATA-2
ヒトやマウスでは6種類のGATA因子があります.血球系で働くGATA因子は,GATA-1, 2, 3です.GATA-2は,造血系組織の他,神経や泌尿器系の発生に働いていますが,わたしたちは,造血系でのGATA−2の役割について,研究を進めてきました. 造血組織の発生は,厳密にプログラムされています.図は,一つの造血幹細胞から,前駆細胞と呼ばれる中間的な細胞を経て,体内で異なった機能を担う,形態的にも異なった様々な血液細胞が分化していく様子を示しています.この分化が進むためには,各ステップにおいて多数の転写因子がプログラム通りに発現し,他の蛋白質を次々と計画通りに発現させていくことが必要なのです. GATA-2の遺伝子が破壊されたノックアウトマウスでは,胎児期早期に死んでしまいますが,一度発生した造血幹細胞が,維持され増殖する段階に異常があることがわかっています.2本ある遺伝子の片方だけが破壊された場合,生き延びる程度に障害は軽いのですが,やはり成体になっても,骨髄造血は,正常マウスと比較すると,障害されています.
・・・このような問題意識のもとに,わたしたちは研究を進めています. |
||
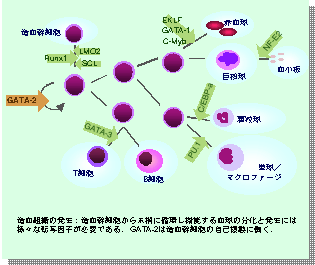 |
||
|
|
||
| GATA-2の遺伝子構造 ー血球系に特異的に発現する第1エクソンを発見 今は全ゲノムの情報がデータベースに登録されていますが,以前は,そういったものはありませんでした.GATA-2を研究するためには、GATA-2の遺伝子構造を明らかにすることが必要でした. マウスGATA-2遺伝子の構造は,2つの第1エクソンがあり,それがどちらも第2エクソンにつながります.翻訳開始点は第2エクソンにあるので,産生される蛋白質は同じなのですが,転写の始まるしくみが,2つのエクソンでは異なっています.ヒトにおいても,やはり第1エクソンが2つあることも明らかにしました. 興味深いことに,近位側の第1エクソン(General first exon; IG exon)は様々な組織で転写されているのに比べ,遠位側にある第1エクソン (Specific first exon; IS exon) は造血幹細胞に近い,Lin-(分化した細胞に出ているマーカーが陰性)分画や,Sca-1+, c-Kit+分画(やはり未熟な細胞を多く含む)のみで発現が認められました. Minegishi et al. http://www.jbc.org/cgi/content/full/273/6/3625 |
||
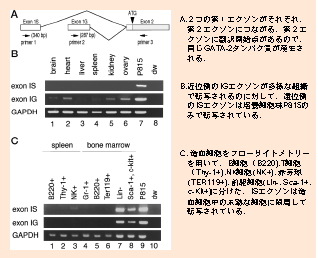 |
||
| GATA-2が造血発生部位であるAorta-Gonad-Mesonephros (AGM)で発現している
続いて,GATA-2の初期造血発生での発現を明らかにしました.In situ hybridization法や,ISエクソンを利用したLacZレポーターを用いたトランスジェニックマウスを作ることで,それらが明らかになりました.ISエクソンを含むGATA-2 遺伝子制御領域に,LacZ染色によって青く発色するレポーター遺伝子(LacZ遺伝子)をつなぎ,トランスジェニックマウスを作製しました.LacZ遺伝子を発現させるしくみは,GATA-2を発現させるしくみを使っているため,LacZ染色で青く発色する組織では,GATA-2が発現していると考えられます.図のAで青い部分は,大動脈や生殖器,将来腎臓になる中腎(Aorta-Gonad-Mesonephros ;AGM)といった組織が発生する部分であり,個体発生の過程で,最初に体内で血液が作られる部分と考えられています.緑色に光る蛍光蛋白質(GFP)をレポーター遺伝子として使用すると,GATA-2を発現して光る細胞が得られます.細胞表面の特徴を解析するフローサイトメトリーという方法を用いると,GFPを発現する細胞は,未熟な血液細胞の性質を持つことがわかりました. Minegishi et al. http://www.bloodjournal.org/cgi/content/full/93/12/4196 |
||
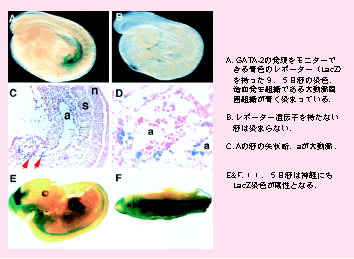 |
||
| 骨髄中の造血幹細胞を可視化できました!
トランスジェニックマウスよりも,より正確にGATA-2の発現を理解するため,GATA-2遺伝子の場所にGFPを入れることで,GATA-2発現をモニターできるマウスを作製しました.(Suzuki, N et al. www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0508928103) 幹細胞は微小環境との相互作用により維持されており,造血幹細胞も骨髄のなかでニッシェと言われる微小環境に依存して存在すると言われています.わたしたちは,GATA-2の造血系に特異性の高いISエクソンに緑色蛍光蛋白質(GFP)をノックインした,ノックインマウスを用いて,骨髄中の造血幹細胞の動画撮影に世界で初めて成功しました. 図は,そのマウスの骨髄です.右側がと同じ領域を蛍光顕微鏡で撮影したものが左側の図です。緑色に強く光る細胞が,造血幹細胞です.造血幹細胞は骨組織に沿う様にして,しかも一つ一つがお互いに離れて存在します.興味深いことに,周囲の血液細胞が活発に動いているのに,造血幹細胞はじっと動きません. この蛍光を目印に,フローサイトメトリーの手法を用いて,造血幹細胞だけを取り出すことが可能です.これらの細胞をもっと詳しく調べれば,一つ一つの造血幹細胞が,いつ分裂しているのか?その時,今までと同じ「造血幹細胞」になるのか?あるいは増殖・分化し,実際に体中で役に立つ「血液細胞」へ育っていくのか?そういった細胞はどんな特徴をもっているか?このマウスを用いて,造血幹細胞の新しい姿が浮かび上がってくるでしょう. |
||
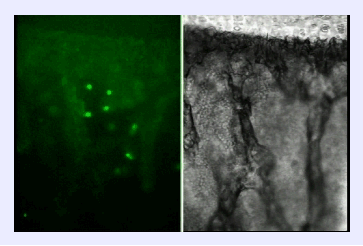 |
||
| GATA-2の分子解剖−1 転写抑制化ドメイン 次は,GATA-2の中に目を向けます. 蛋白質の中で,部分(ドメイン)ごとに,異なる機能を分担しています.GATA-2は転写因子ですので,DNAに結合する部分と,転写を活性/抑制化する部分があるはずですが,今まで転写活性化の詳しい仕組みはわかっていませんでした.
|
||
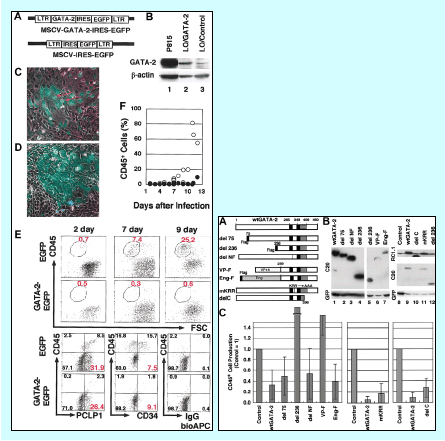 |
||
| GATA-2の分子解剖−2 ユビキチン化
GATA-2が機能する細胞では,GATA-2を作ること(発現),GATA-2を壊すこと(分解)の両方を通じて,GATA-2のON/OFFスイッチが調節されていると考えられます.そこで,GATA-2が壊される時にはどのようなシグナルがどこに入るのか,を調べました. →下図には、Nフィンガー(NF)とCフィンガー(CF)を持つGATA2蛋白質を示しています。GATA-2にはN末端、C末端、NフィンガーのN側と、3つの分解に関わるドメインがあることが明らかになりました.DNAに結合するNフィンガーとCフィンガーは他のGATA因子と比較的似ていまが,分解に関わるドメインはこれらは他のGATA因子と相同性が低い部分であり,GATA1とGATA-2での分解機構の違いがあると考えられます.N末端側の分解ドメインは,転写活性化機能も持っています.ユビキチン化と転写活性化能との関連は他の転写因子でも指摘されるところであり,このような分解と結びつく蛋白質の修飾が,同時に下流遺伝子の転写活性化をもたらす分子機構の解明は興味深い課題です. Minegishi et al. Genes to Cells, 2005 |
||
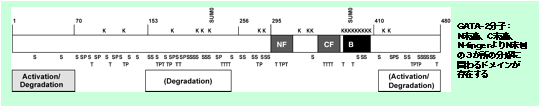 |
||
| 転写因子GATA-2自身の転写調節機構
GATA-2自身の転写調節のしくみを探ることは、GATA-2の発現を指令している転写因子を知ることにつながります。GATA-2の発現を開始させるシグナルは?それは造血組織の発生や、一度できた造血幹細胞の自己複製、増殖にどのように関わっているのでしょう? GATA-2の転写は、非常に広い転写調節領域によって調節されています。共同研究者のEngel教授の研究室では、大腸菌人口染色体(BAC) を用いて、GATA-2遺伝子の上流や下流の数100キロ塩基対 (kbp) の範囲の解析を進めています。造血に関わる転写調節領域は、250 kbpのBACを使って明らかにされました。 わたしたちは、GATA-2のISエクソン上流3.1 kbpの範囲に、造血系で働く転写調節領域があることを明らかにしました。3. 1bbp上流域を、GFPの転写活性化領域として用いた遺伝子を用いてトランスジェニックマウスを作成すると、胎児の造血組織 (AGMなど)がGFPの発現により緑色に光ります。そして、ヒトとマウスとの間で塩基配列相同性が非常に高い、-2.8〜3.1 kbp の範囲の解析を進めています。 右図Aは、-2.8〜3.1kbpの領域の塩基配列、BはD3.1構築に少しずつ変異を入れた配列のトランスジェニックマウス解析の結果、CはBで示した各々の構築について、代表的な個体の写真を示しています。まず、Aに示す通り、-2.8〜-3.1kbp領域には、GATA因子結合配列が6か所あります。そして、その各々に変異を入れた構築でトランスジェニックマウスを作製すると、もしも、変異を入れたGATA配列が重要であれば、GFPの光り方が変わってきます。D3.1構築は、胎児期の造血組織である大動脈と卵黄嚢、肝臓原器がひかりますが、Bをみると、造血組織である大動脈でGFPが光るためには、GATApal以外の配列はどれも必要であり、GATA-2の発現にとっては、いずれかのGATA因子がこの領域に結合することが必要なことがわかりました。 その他、 -2.8〜3.1kbp領域中にはその他の転写因子が結合する候補となるような配列が多数存在し、その一つ一つについて、解析を進めています。 Kobayashi-Osaki et al. Mol Cell Biol 2005 http://mcb.asm.org/cgi/content/full/25/16/7005?view=long&pmid=16055713 |
||
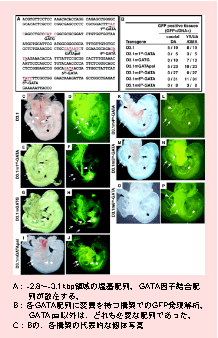 |
||
| GATA-2についての文責は小林 牧です.ご質問はmaki_k@tara.tsukuba.ac.jpまでお寄せください. |